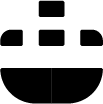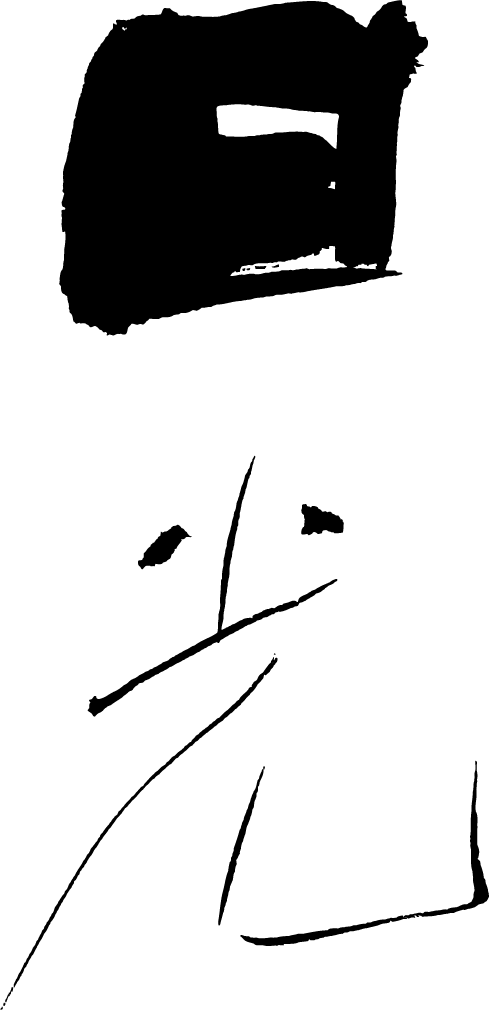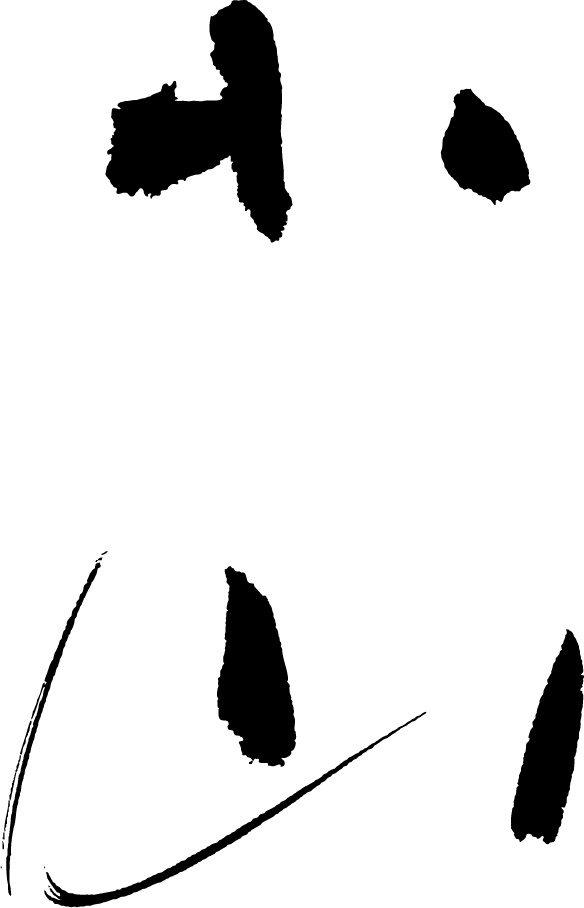Spec & Technology
真のジャパニーズウイスキーとは何か。
その暫定解を刻む。
この問いに、唯一の正解はない。
百五十年余にわたり
日本酒を醸してきた酒蔵として、
ひとつの「暫定解」をウイスキーとして提示する。
ウイスキー『哲/TETSU』は、
問いを立て、考え、判断し、
その責任を酒として引き受けるシリーズである。
日本の歴史・文化・精神を、
ウイスキーという舞台に映す。
私たちは、日本酒蔵としての矜持をもとに、
精神性・手仕事・風土と向き合う姿勢を、
世界の酒文化に重ねあわせ、新たな形で表現していく。
定型や前例にとらわれず、
日本酒の発酵文化と和酒の叡智を総動員し、
日本固有の歴史・文化・伝統を映す一本を探究する。
異なる文化、その「差異」こそ、
対立ではなく生成を生む。
東洋と西洋、和酒と洋酒。
異なる文化は、織り込まれ、響き合い、
新たな価値を生む。
文化とは、差異が交わり、
生まれ変わり続ける営みである。
当代の革新は、やがて未来の伝統を芽吹かせる。
その生成の只中に、
哲学するウイスキー『哲/TETSU』がある。
日本酒造りにおける「吟醸思想」を、
ウイスキーで体現する。
私たちが目指しているのは、
効率の良いウイスキーではありません。
「吟醸(Ginjo)」とは、
効率よりも丁寧さを選び、
酒の中に上品さと品格を残そうとする、
日本酒造りの思想です。
ウイスキー『哲/TETSU』は、
この「吟醸(Ginjo)」思想を、蒸留酒の世界で引き受けます。
効率を捨て、品格を選ぶ。
下記に記す私たちのウイスキーの製造プロセスは、
いずれも効率的ではありません。
しかし私たちは、
速さや量ではなく、完成後の品格と、
日本固有の酒造精神の体現を優先します。
時間と手間を惜しまないことは、
結果として品格ある個性と酒の佇まいに現れる。
それが、ウイスキー「哲/TETSU」の信じる基本姿勢です。
清酒酵母 100% での発酵「日本酒技術の応用」
日本酒蔵の核である「発酵」の主役、清酒酵母のみを用いた発酵。
従来は、麦芽との相性から困難とされてきた清酒酵母100%発酵を、
酒母や段仕込みの知恵を応用することで実現。
日本固有の吟醸香の引き出しを優先し、一般的なディスティラー酵母(ウイスキー酵母等)が求める収率・効率性は追わない。
洋のウイスキーに、和の酒造りの叡智を注ぎ込む挑戦である。
一番麦汁のみを使用
清酒酵母の特性を最大限に引き出すため、
抽出効率を高めるための後半麦汁は使用せず、
一番麦汁のみを用いて仕込みを行う。
歩留まりを犠牲にする代わりに、
雑味の少ない、澄んだ酒質を得る。
効率を捨て、品格を選ぶ。
この工程は、その姿勢を最も端的に表す。
「吟醸造り」に通じる、長期低温発酵
発酵は速さを競う工程では無い。
私たちは、時間をかけることを選ぶ。
清酒酵母の特性を最大限に引き出すため、
「吟醸造り」と同様の長期・低温発酵を採用。
「吟醸造り」で発酵由来の荒さを抑え、
繊細な吟香や華やかな果実香を引き出し、
透明感と気品のある香味構造を育む。
これは効率ではなく、
完成後の佇まいを優先する判断である。
香りを守るための「減圧蒸留」
銅板による改造を施した、
国産ステンレス製の減圧蒸留器を導入。
通常よりもはるかに低い温度で蒸留する「減圧蒸留」と、
「常圧蒸留」を組み合わせる蒸留の独自設計によって、
発酵由来の繊細な香味成分を損なわず、
雑味を抑えた透明感のある酒質を生み出す。
日本酒の「吟醸造り」の姿勢に通じる、丁寧で緻密な蒸留哲学である。
酒米由来の「吟醸粉」を用いたグレーン設計
日本酒造りの精米の過程で生まれる、
米の中心部(心白)に近い最高水準の
吟醸粉(酒米)をグレーン原料に使用。
米特有の柔らかで上品な甘みと旨みが、
ウイスキーの中に静かに溶け込み、
他にはない日本的な輪郭を形づくる。
日本酒蔵固有の副産物を活かすこの選択は、
日本古来の循環と持続の酒造思想をも映す。
国産木材による「和樽」熟成
日光杉をはじめとした国産木材を用いた和樽による熟成は、
ジャパニーズの未踏領域。
爽やかな杉香や穏やかな甘みを酒に映し出し、
世界でもここでしか得られない風味を形づくる。
日本の自然と工芸が融合した熟成文化を、
新たに切り拓いていく試みである。
風土を活かした複数の熟成環境「小山・日光・大谷」
小山の寒暖差の激しい平地、日光の冷涼な森林地帯、大谷の地下採掘場──
異なる風土と環境がもたらす熟成環境を掛け合わせる。
気温・湿度・地質の差異がウイスキーに多層的な表情を与え、
複雑さと奥行きを生む。
ひとつの蒸溜所でありながら、
多彩なテロワールを体現する熟成である。
国産モルトの使用「栃木県産・二条大麦」
栃木県は全国一の二条大麦産地。
肥沃な穀倉地帯で育まれる県産モルトを積極的に採用することで、
地の風土を酒に映し出す。
地の風土をそのまま映す、"地ウイスキー"の矜持を示す選択である。
井戸から湧き出す「日光山系の自然伏流水」が仕込み水
小山市は、二荒霊水をルーツとする日光山系の伏流水に恵まれてきた。
江戸時代より酒造りが盛んだった背景には、
この「程よく硬い中硬水」がある。
清酒では吟醸香を、ウイスキーでは上品で厚みのある味わいを生む──
創業当時から涸れることなく湧き続ける蔵の井戸水が、
今も全てを支えている。
Exploration
真正ジャパニーズウイスキーの暫定解
真のジャパニーズウイスキーとは何か──。
その問いに暫定解を刻み続けることこそ、私たちの使命である。
清酒酵母や吟醸粉、和樽、そして日光の水と風土。
試みと挫折、そして再挑戦を繰り返す探究の中から、日本酒蔵ならではの哲学するウイスキーが生まれた。
その独創性と革新性は、アジア最大級の品評会TWSC2025で
「INNOVATOR OF THE YEAR(ベストディスティラリー賞)」として評価され、
さらにローマ教皇庁や台北駐日経済文化代表処への献上という
歴史的な瞬間を刻むに至った。
しかし、哲は完成を拒む。
次なる問いが、常に私たちを待っている。
探究は続き、暫定解は未来へ更新されていく。